こんにちは。
巫女の岩瀬愛梨です。
最近、朝夕と冷えてまいりました。皆様、風邪をひかないようにお気をつけてください。
さて、時間が空いてしまいましたが、久しぶりに神様紹介をしたいと思います。
前回は、「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」の神話の中でも有名な因幡の白兎についてご紹介しました。
本日は八十神の迫害についてご紹介します。
八上比売を娶ることになった「大穴牟遲神(おおなむちのかみ)=大国主大神」を妬んだ八十神は、大穴牟遲神を殺そうとします。
まずは大穴牟遲神を山のふもとに連れて行き、赤い猪を追いおろすから捕えよと命じて、猪に似た大石を火で焼いて落としました。大穴牟遲神は石の火に焼かれて死んでしまいました。
大穴牟遲神の母である「刺国若比売(サシクニワカヒメ)」は悲しんで高天原に上り、カミムスビに救いを求めます。
カミムスビはキサガイヒメとウムギヒメを遣わし、この二神の治療により大穴牟遲神は生き返りました。
しかし、八十神はあきらめません。今度は大木を切り倒し、切込みを入れて割れ目を作り、その割れ目に楔を打ち込んでふさがらないようにし、その割れ目に大穴牟遲神を入れ、楔を引き抜き挟み殺しました。
それを悲しんだ刺国若比売は大穴牟遲神を見つけ出し、再び生き返らせました。
そして、刺国若比売は大穴牟遲神を八十神から逃がすため木の国の大屋毘古神(おおやびこのかみ)の元へ避難させました。
しかし、八十神が追ってきて大穴牟遲神を引き渡すように迫ります。そこで大屋毘古神は大穴牟遲神をこっそりと逃がし、根の国の素蓋鳴神(スサノオノカミ)を尋ねるようにいいました。
こうして大穴牟遲神は根の国へ向かったのです。
本日は八十神の迫害についてご紹介しました。二度も大穴牟遲神を助ける刺国若比売はなんとも優しい母神ですね。
初宮や七五三にいらっしゃる親御さんたちもとても優しい目をしております。
お子様の健やかな成長をお祈りする場合は実咲社へお参りください。実咲社には子育てのお狐様がいらっしゃいます。
初宮や七五三のご祈祷でお渡しする子育て絵馬はこちらのお狐様にご奉納ください。




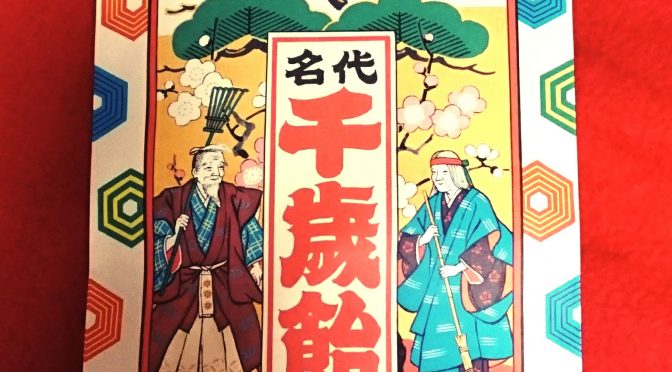

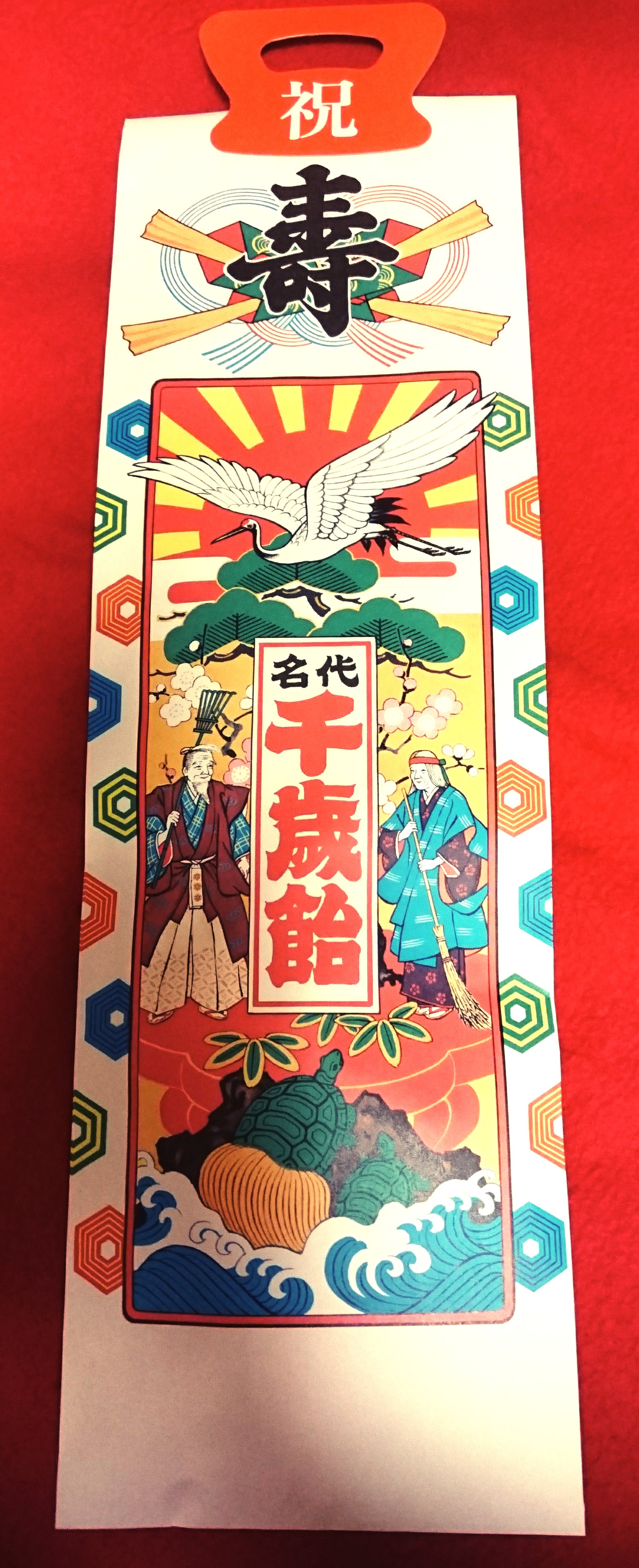




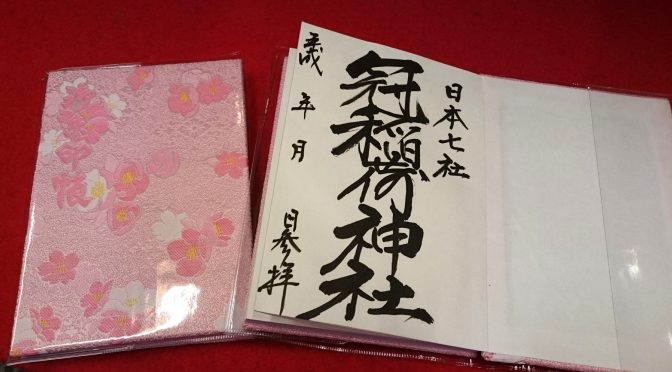

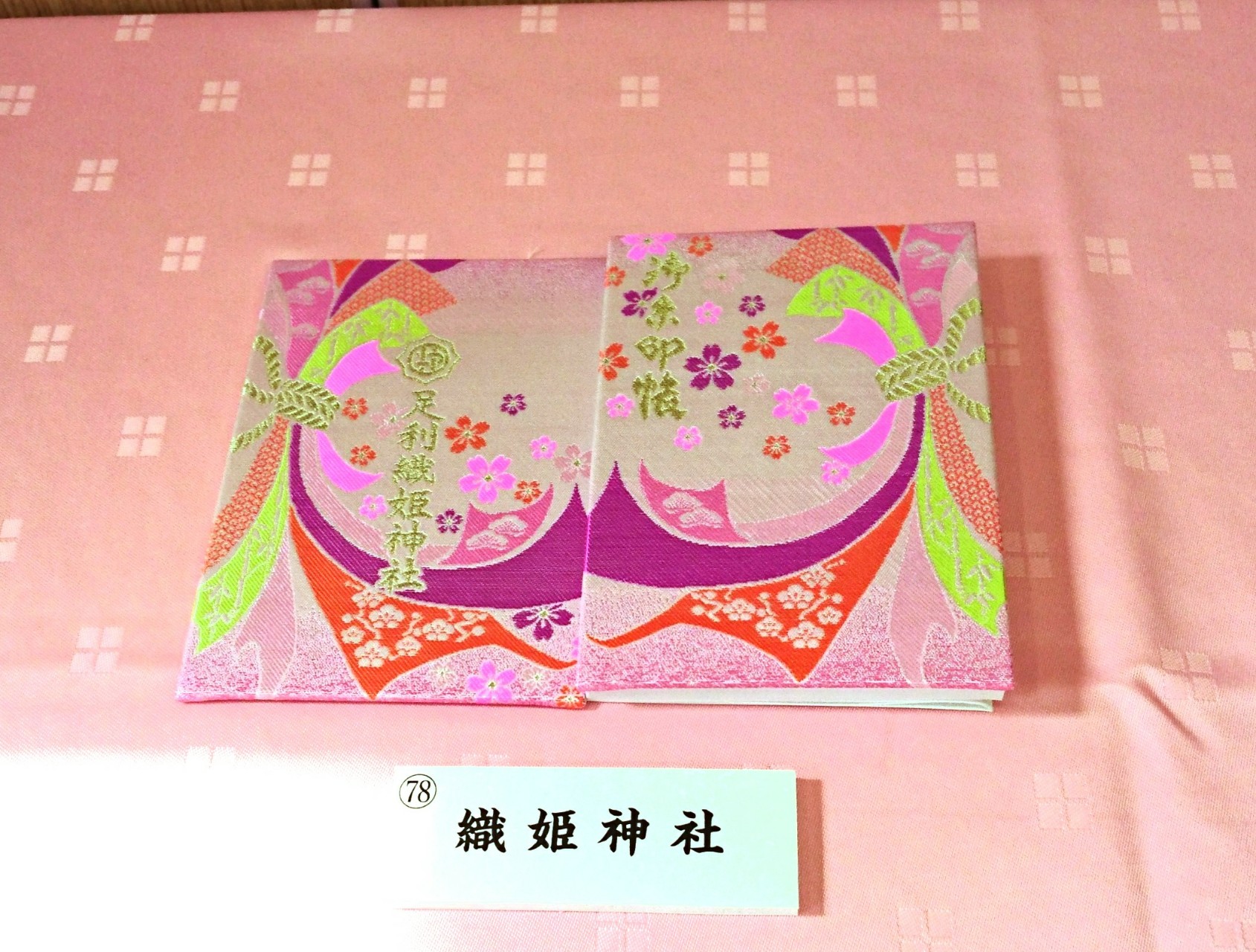




 白無垢に綿帽子がとってもお似合いの新婦さま…の後ろ姿でスミマセン。。。
白無垢に綿帽子がとってもお似合いの新婦さま…の後ろ姿でスミマセン。。。

























